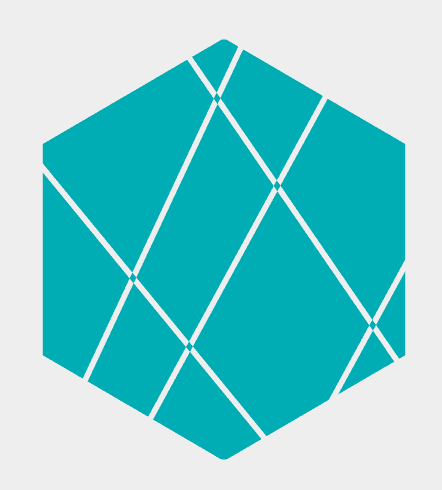「終活」という言葉が世間に広まったのは2009年頃と言われています。2012年に41歳の若さで亡くなられた流通ジャーナリストの金子哲雄さんが終活を行ったことが、その普及に大きく貢献したという説が有力です。
終活に関するセミナーや相談会で、よく耳にするのが「縁起が悪い」「面倒くさい」「まだ早い」「考えたくない」といった言葉です。このような方々には、私たちは問いかけます。「お子さんが夏休みの宿題をせずにいた時、どんな言葉をかけましたか?」と。
「早く終わらせて、後でゆっくり遊んだ方が楽だよ」「やらなければならないことは、先に終わらせてしまいなさい」「やらなくて困るのは自分だよ。2学期に先生に叱られるのも自分だよ」これらの言葉を思い出すと、多くの方が表情や目の色を変えられます。そして、私たちの言葉を「砂が水を吸うように」受け入れ、終活に取り組まれるのです。
夏休みと2学期の始まりは、日程が決まっています。では、終活の始まりと終わりはいつでしょうか?終わりを亡くなった時とするならば、始まりはいつなのでしょうか?
せっかく終活という言葉を知り、考える時間があるのに、認知症などでその機会を失ってしまうのは、非常にもったいないことです。