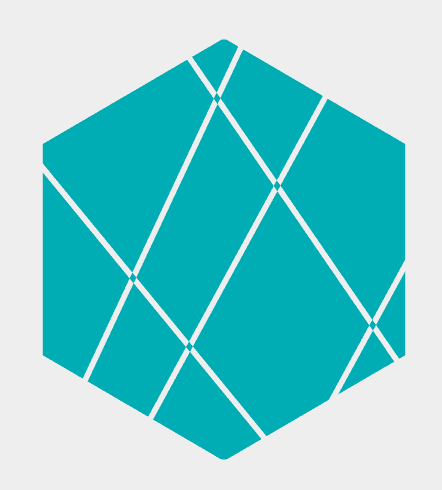「孤独死」は、誰にとっても避けたい事態です。先日、著名な方が亡くなられたニュースは、社会に大きな衝撃を与えました。しかし、「孤独死」の定義は、実は曖昧なのが現状です。核家族化が進み、同居が減少する現代において、自宅で家族に看取られて亡くなるケースは年々減っています。
例えば、高齢者の単身世帯が多い東京都豊島区では、こたつでうたた寝中に急変し、誰にも気づかれずに亡くなるケースも「孤独死」として扱われます。しかし、そのような最期を迎えた方が、本当に「孤独」を感じていたのでしょうか?
一般的にイメージされる「孤独死」は、誰にも発見されず、時間が経過してから見つかるケースでしょう。孤独死の平均発見日数は18日と言われています。しかし、3日以内に発見されるケースも41.8%存在し、その内訳は男性39.7%、女性48.1%です。女性の方が発見が早いのは、地域コミュニティとの繋がりや、日常的な買い物などで外出する機会が多いことが理由と考えられます。
このような「孤独死」を回避するためには、以下のような対策が考えられます。
人感センサーの設置
企業や団体の安否確認サービス(LINEなど)の利用
宅配弁当や食材配達サービスの利用
行政による見守りサービス
これらの対策に共通するのは、「自ら行動を起こす」ことです。民間サービスは有料ですが、孤独死を避けたいと願う方々への対価と言えるでしょう。行政サービスは地域によって異なるため、確認が必要です。
しかし、私たちが最も避けたいのは「孤立死」です。社会との関わりを望まない方や、拒絶する方が一定数いるのも事実です。その選択は尊重されるべきですが、周囲との関係を断つことが、結果としてリスクを高める可能性があります。
「孤立死」から「孤独死」へ、あるいは発見までの日数を18日から3日へ短縮できるかどうかは、ご自身の行動と決断にかかっています。